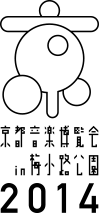音博の楽しみ方 その7
京都音楽博覧会2014に登場する海外勢四組の楽しみ方
「このブッキングが自分たちの今を写し出す鏡のようになっているんです」
対談:岸田繁×サラーム海上
~現地に行くと音の魔力があるというか、すごくハマったんです
岸田繁(以下「岸」)「サラームさんは高崎出身ですよね。高崎にいた頃は世界の音楽に触れる機会はあったのですか」
サラーム海上(以下「サ」)「高校を卒業する1985年まで高崎にいましたが、当時は主にFMラジオを聴いてエアチェックしてました。NHK FMで坂本龍一さんが『サウンドストリート』という番組を、民族音楽学者の小泉文夫先生が『世界の民族音楽』という番組をやっていて、それでインドネシアのガムランやブルガリアのポリフォニーなんかを知ったんです。あとは『クロスオーバーイレブン』(1978年から2001年まで続いたNHKFMの伝説的深夜番組)ですね」
岸「おお、めっちゃ好きでした! あのナレーション(笑)!”今日と明日が出会う時”(番組のナレーターの真似をする)」
サ「今、僕がNHK FMでやらせてもらっている『音楽遊覧飛行 エキゾチッククルーズ』も『クロスオーバーイレブン』の流れをくんでいる感じ。ちなみに7月は『寓話、伝説の音楽』特集と題して、世界の宗教儀式音楽や伝承音楽ばかり流しました。たぶん放送事故みたいに聞こえたはずです(笑)」
岸「僕はそれを朝から日課のように流しています」
サ「ありがとうございます。ところで今日は京都音楽博覧会に出演する四組の海外組の話ですね」
岸「ヤスミン・ハムダンのアルバム『YA NASS』が本当に良くってですねえ! 僕はどこの国の音楽でも、いわゆるフォークロア(民俗音楽)、伝承音楽は好きなんです。そうした音楽を欧米の音楽というか、北半球で流行っている音楽(ポップ音楽)に近づけたものに、たまに面白いものがあるじゃないですか。最近は1982年のMonsoon(インド古典声楽を学んだインド系イギリス人の少女シーラ・チャンドラをフィーチャーしたニューウェイヴ・バンド)のレコード盤を手に入れて、毎日聴いているんです。最初の頃のM.I.A.とか、伝承音楽のメロディーやスケール、和声などを下敷きにした、その時々のポップスやダンス音楽なんかも大好きで……。かつてのブラジルのミルトン・ナシメントやムタンチス、エグベルト・ジスモンチら、ブラジルの人が西洋音楽をガチでやろうとしてる感じとかも、ちょっといなたい感じが好きなんです」
(Monsoon "Ever So Lonely" MV)
岸「中東や東欧のメロディーは日本の唱歌とかと繋がって聞こえますね。僕はきちんと音楽教育を受けているわけではないのですが、クラシックは大好きなんです。でも、モーツァルトやヨハン・シュトラウスみたいなベタなクラシックはあまり好きではなかったのですが、ウィーンに行ったとき、それがすごく良く思えるようになったんです。やっぱりその場所の力なのか、ミュージシャンがきちんと消化しているからなのか……、現地に行くと音の魔力があるというか、すごくハマったんです。ウィーンでアルバムのレコーディングをしていた時に、弦のアレンジをしてくれた人がバルトークやショスタコーヴィチ、ラヴェルみたいないわゆる”難しい音楽(笑)”が好きな人で、彼のおかげで」
サ「日本にいるとワケのわからない音楽にしか聞こえなかったものが、現地に行くと腑に落ちることってありますよ」
岸「それはちょうど音博を始めた年で、なぜかタラフ・ドゥ・ハイドゥークス(ルーマニアのロマ=ジプシー楽団、超絶演奏により日本でも人気が高い)を呼ぶことになったんです(笑)。彼らはなかなかデタラメな連中で、集合時間に来ないとか、スタッフがサングラスを取られたとか、面白いエピソードがいっぱい残りました。その日は大嵐が来ちゃって、ライヴが出来るのだろうかという状態だったんですが、彼らはすごい演奏をしてくれたんです。その時、彼らはバルトークの『ルーマニア民俗舞曲』などを完全コピーするということをやっていたんです。それを聞いて、自分の中で何かが繋がったんです」
(タラフ・ドゥ・ハイドゥークス「ルーマニア民俗舞曲」MV)
~第二の音楽の青春を中東音楽で過ごしているんです
岸「ウィーンには沢山トルコの移民が住んでいて、小さなスタジオでレコーディングしていた時に、横のスタジオから、ずっと間違っているような聞いたことのない音楽が聞こえてきたんです。最初はヘタなのかなと思っていたんですけど、毎回間違っている。これは何かの法則性を持って間違っているな、何なんだろう?と思っていたら、トルコ人が出てきて、彼らの携帯の着信音が、彼らが演奏していたのと同じような音楽だった。”それってなんなん?”と尋ねたら、”トルコで一番流行っている曲や”と言われたんです。それが気になっちゃって。というのも、その音楽の感情がわからへんから。例えば日本人なら童謡を聴けば、日本昔話みたいな気分になるし、西洋映画を観て育っているから、ムーンリバーを聴けばうっとりするし。そのトルコの音楽からはそういう部分がわからへん。ただ忙しい感じ(笑)。その後もウィーンでトルコ人と話したり、レコーディングに東欧の人達が参加してくれて、多くはウィーン・フィルなんかの人ですが、中には譜面の読めない人も来ていて。自分の聴いてきた欧米の音楽とは違う部分、そのルーツを自分の音楽と繋ぐ作業が始まったんです」
サ「それをウィーンで感じたとは羨ましい。ウィーンはかつてヨーロッパの南東の境界、そこから先はオスマン帝国領でしたからね」
岸「くるり自体は結成してから18年も経っていて、僕も相方もわりと”掘る人”なんで、色々聴いてきました。でも、この五年くらいはちょっと音楽的に守りに入っていた時期で、あまり新しいものに感化されずにシンガーソングライター的にやろうかなと思っていたんです。しかし、それもここ二年くらいでまた変わってきました。
震災があって、音楽を聴けなくなった時期があったりもしました。政治や社会の動きがミュージシャンの音の方向性やアティチュードに影響せねばならん、みたいな雰囲気もあったし。自分にもそういう部分もありますよ。でも、その向こう側に立ち返って、音の無邪気さを楽しむ、自分たちで音を鳴らす。すると、バカらしい音だったり、怖いけど面白い音、知らないけど知ってるのかもしれん音、そういうのをサウダージと言うんかな? そういうのもあって、自分の中では中東などの音楽が今一番そういうのがあるように聞こえるんです。サラームさんが以前ラジオ(NHKFM『音楽遊覧飛行エキゾチッククルーズ』)でかけていた、『Cocktail』というインド映画の主題歌とか、すごいダサいハウスなんだけど、ハマってしまって(笑)」
サ「ボリウッド映画音楽の『Tum hi ho Bandhu』ですね! あれは本気でダサいですよね! でも僕も大好きで、DJでいつもかけちゃってます!」
岸「あれは欧米の音楽だけ聴いていて、それを基準に”これはイケテる、これはイケテない”と言うのと全然違う感覚があって、音楽を聴くのがまた楽しくなった。ダサイものから高尚なものまで、すごく楽しくなって。第二の音楽の青春を中東音楽で過ごしているんです」
サ「そこまでハマるとはすごい!」
(映画Cocktail『Tum hi ho Bandhu』のMV)
~思い浮かべていた風景とまったく同じだった
岸「デビューした頃に書いた『東京』という曲があります。自分たちは東京の生まれじゃないし、東京に遊びに来た時に五分くらいで書いた曲だけど、それをイイと言ってくれる人が多くて、自分ではよくわからないままライブでもやってきた。でも、15年くらい歌った頃から、あれは結局、風景を描いた映像喚起させる曲なのかなと思ったんです」
(くるり『東京』のMV)
岸「ヤスミンの『ベイルート』という曲を聴いて、後になってそのMVを観たとき、そこに写っていた風景は、それまで自分が思い浮かべていた風景とまったく同じだったんです。これはすごい曲だなあと。レバノンやベイルートと言っても、日本人の98%くらいはどこにあるのかも知らないでしょう、でも、ちょっとでも音楽を好きな人だったり、芸術に理解のある方なら、あの曲を聴けば、サウダージがあるというか、強さじゃない、何か”お出汁”のようなものを感じるはず。
僕は刺激のある音楽も好きだし、音楽の中の技術的な面も好きです。でも、たまに優れたソングライターがポっと出す”孤独なつぶやきみたいなものが世界中の人達に伝わってしまった”みたいなのが好きで。あの曲には久々にそれを感じたんです。アルバムの全曲が良い曲とは思わへん。でも、一曲目があんな感じで(アコースティックギターからジワジワ)始まっているのもイイし、デビューしたての人ならではの未整理な感じもイイ。アラビア語で歌っているのに、イギリスから出てきた新人みたいな感じ。流行りに寄せてるのか、寄せてないのかわからへんけど、たまたま時代の空気を読んでしまったみたいな、優しい、暖かい感じ。日本人の女性シンガーと似てる感じもするし。ライブが楽しみです」
サ「彼女のスタジオライブを数曲聴いたけど、未完成な感じがイイですね」
岸「僕も女性のギタリストと二人でやっているライブ映像を観ました。眉毛をつないで描く化粧をしていて、そういう所も面白そうです。ところでベイルートってどんな町なんですか?」
サ「ベイルートは地中海に面した港町で、一見快楽的なんだけど、頻繁に爆弾テロが起こるので、外国人旅行者が誰一人いないんです。同じアラブ人である湾岸諸国の人でさえ退去命令が出たりもします。今ではドバイに代わられてしまったけど、1975年の内戦以前は『中東のパリ』と呼ばれた中東一の国際都市だったんです。日本人の駐在員も沢山いたそうです。レバノン人は国内に400万人、国外に800万人がいて、日本で一番有名なレバノン人は日産のカルロス・ゴーン社長でしょう。彼らはまめに海外に行き来しているので、外国人がいない今も国際的な雰囲気が残っています。レバノン全体は地中海に沿って南北に山脈が続き、海沿いの町はどこも熱海みたいな感じ。春に行くと、午前中に山でスキー、午後に地中海で泳げるらしいです。そんな不思議な気候です」
岸「音楽シーンは?」
サ「ヤスミンもフランスですが、アーティストの多くは海外に移住してしまい、さすがにシーンは小さいです」
岸「そんな危険な所になぜサラームさんは通ってるんですか?」
サ「食べ物が美味しいんですよ! レバノン料理は中東で一番、世界でも有数の美味さだと思います。肉、そして野菜の味が濃い! レバノンは聖書で『乳と蜜の流れる土地』と描写されるカナンの地の一部なんです。例えば、オリーブオイルもワインもビールも現在のレバノンの地で世界で一番最初に作られたんです。パリやロンドンに行けばレバノン料理店は沢山ありますが、現地で食べる生の山羊肉のたたき、クッベ・ナイエやパセリのサラダ、タッブーレは最高です。いつかお連れしたいですよ」
(ヤスミン・ハムダン「ベイルート」のMV)
~そこに椎名林檎がいるのがバランスになっている
サ「アルゼンチンのトミー・リブレロは、初めて聴いても一緒に歌えるメロディーが印象的ですね」
岸「彼の一作前のアルバムを聴いたら、ダンサブルな曲も多くて、一枚の中でいろんなことをやっています。僕はいろんなことをやっていて、でも、四曲目くらいにアコースティックなイイ曲が入っているという作りのアルバムが好きなんです。僕がいろんな人に彼のことをイイと言っていたのを聞いていたマネージャーがネットで連絡先を見つけ、メールすると、すぐに出演してくれることになった(笑)。アルゼンチン音楽ではフアナ・モリーナが大好きですが、今回はもうちょっと明るい音楽がいいなと思って。トミーのやってる音楽はアルゼンチン的というより越境的だし」
サ「そうですね。楽器を持って行進しながら演奏してる感じがアメリカのベイルートなど、今のシンガーソングライターっぽくてイイ」
岸「ちょっとチンドン的な感じも」
(トミー・リブレロのMV)
岸「万国博覧会じゃないけど、音楽博覧会という名前を付けたからには、いろんな国、いろんな地域から音楽家を呼びたい。一年目はとにかくデタラメをやろうということで、タラフ・ドゥ・ハイドゥークスを呼んで、小田和正さんを呼びました(笑)。ただ、興行としても大きいし、行政と話をしたり、公園や近隣の住民の方々とバランスを取りながらやっているので、”二日間、フェスやりますよ!Yeah!”みたいなノリでは出来ない。でも、それを逆にメリットにして”アコースティックで!”と言うところで始めました。でも、集客のこともあって、ここ2~3年は売れている人で固めていました。それはそれで楽しかったですね。ブッキングも自分たちでやっているので、自分たちのモードがすごく反映されるんです。今回はたまたまアルバムを作っていたので、アルバムのアティチュード、アトモスフィア? よくわかんないですけど(笑)、このブッキングが自分たちの今を写し出す鏡のようになっているんです。
でも、それだけでは音博になっていない。そこに椎名林檎がいるというのが、僕らのバランスになっていると思います。僕らの中の暴力的な部分なのかもしれません。僕は食べ物が大好きで、最初の皿から最後の皿まで食べる時、箸休めの時にどれだけ面白いものを出してくれるかが重要なんです。古式ゆかしい料理ってありますよね、京都の懐石やイギリスのティータイム……」
サ「フルコースのフレンチとか?」
岸「そうそう、中国の宮廷料理も。そういう料理にあるエスプリ的なものも好きですが、パンチのある変化も好きなんです。デタラメなもの。手塚治虫的、藤子不二雄的、あるいはつげ義春的な漫画も良いのですが、そこに赤塚不二夫が入ってきた時というのがたまらなくて(笑)」
サ「ハハハ、それ、フジオ・プロ社長の赤塚りえ子(赤塚不二夫の長女)さんに伝えますよ。赤塚不二夫の漫画はすごいですね。何と言ってもナンセンスすぎて外国語に翻訳出来ない。他の有名な漫画家は外国でも知られているけど、彼だけは翻訳出来ないから外国で知られていない」
岸「なるほど。あの感じがコース料理の中に出てきたら、それだけでクリティカルヒットです。それだけでアルバム二枚作れそうなくらい(笑)」
~白でも黒でもない、茶色い人達の暗躍を無視できない
(サム・リー the ballad of George CollinsのMV)
サ「サム・リーは本当に面白いですよね。イギリスのトラッドを本格的にやってるけど、本人は東欧系のユダヤ人だという。自分の音楽史を話させてもらうと、僕は80年代初頭のニューウェイブからロックに入りました。YMOからやジャパン、スペシャルズ辺りが入り口です。たとえばスペシャルズの『ギャングスターズ』のエキゾチックなメロディーに惹かれていたのですが、今聴くと、あれはタラフ・ドゥ・ハイドゥークスそっくりに感じます。というのも彼らはジャマイカ系と白人のバンドだと思っていたけど、その白人はイギリス人ではなく、東欧のユダヤ人で、結局あのメロディーは東欧から来たものだった。肌は白いけど、中身は白でも黒でもなく、こういう言い方して良いのかわからないけど、その中間の茶色の人達だったんです。
アメリカのロックンロールも”黒人のリズムにアングロサクソンやケルトのメロディーを足して”と大ざっぱに言われるけど、東欧移民がもたらしたポルカのメロディーも大きな影響があるじゃないですか。サーフロックにはギリシャ移民の音楽の影響もあります。これまであまり気づかずにいたけど、僕は20世紀の欧米のポップ音楽においては、白でも黒でもない人達の暗躍を無視できないと思っているんです」
岸「和声の内声やカウンター、東欧人やユダヤ人は西洋音楽の中でそうした部分を繋いできたと思うんです。クラシックに関して言えば、モーツァルトは真っ白で全部きれいすぎる。どれだけメロディアスな曲でも純度が高すぎてメロディーに聞こえないくらい。それはそれで好きだけど、チャイコフスキーを聴くと、モーツァルトとは全然違って、ちょっとダサイけどカッコイイ。どこかオカマ臭いけど(笑)、みんな泣くよね、とか。チャイコフスキーもロシアだから」
サ「ブラジル音楽においてもジスモンチがレバノン系だったりする。すると、僕はやはり白でも黒でもない人達の音楽が昔から好きだったんだなあ」
岸「音楽の中にそういうことを発見すると一番平和な気分になりますね」
サ「だからサム・リーも、音楽的にはイギリスのトラッドだけど、東欧のユダヤ系だからこそイギリス人が気がつかなかったことをやれる。ノラ・ジョーンズだって、ラヴィ・シャンカルの娘で、インドの血が入ってるからこそ、あんなアメリカーナを再発見したんじゃないかな。あれは長い間、ウィリー・ネルソンくらいしかやってなかった音楽ですよ」
岸「それって面白いですね」
(スペシャルズのギャングスターズMV)
~変わり続ける人も良いけど、変わらない人も良い
サ「最後はペンギン・カフェ。1980年代初頭のペンギン・カフェ・ブームって覚えていますか? 西武セゾン系カルチャー真っ盛りの時代」
岸「いえ、その頃は僕はまだ子どもで、音楽を聴き始めてなかったんです」
サ「2年前に東京で行われた彼らのライヴを観に行ったのですが、その頃若者だった、現在50代のオッチャンたちが当時風の黒いジャケットを着て集まっていました(笑)」
岸「そのままインテリアとして飾れるようなお洒落なレコードジャケットを覚えています。あれは持っとかなぁアカんアルバムって感じで、いろんな人の家に置いてありましたもんね。具体的にどんな内容だったか僕は思い出せないけれど(笑)。音楽的に言えば、彼らはイギリス的すぎて僕には少々ピンと来ないところもあるんですよ。でも、リーダーのアーサー・ジェフスはお父様が亡くなられた後、その音楽性をしっかり受け継いでいる。以前、音博にはヴェンチャーズに出てもらったこともあるんです。それと同じで、彼らは現代の伝承音楽になっているものとして価値があると思うんです。彼らの新作を”15年前の作品ですよ”と言われても信じてしまう。それはAC/DCをいつ聴いてもロックであるのと同じ。変わり続ける人も良いけど、長く続けている変わらない人も良い」
サ「ライブでも父親サイモンが作った80年代初頭の曲をそのまま演奏していました」
岸「彼らは一つのジャンルを作ったと思うんです。ともすれば流されてしまいそうな音楽(イージーリスニング的)なのに、それを職人気質、音楽至上主義、と言うと軽いけど、そんな感じでやっている。大勢の人の前であの音楽が鳴るというのもすごくキャッチーなんじゃないかと思います」
(ペンギンカフェ、80年代の曲のライブリハ)
サ「ところで僕は音博にまだ行ったことがないんですよ」
岸「会場は大きな縦長の公園で、12,000人くらい入れます。公演の片側には蒸気機関車が演奏中でも走っているんです。反対側には水族館があって、イルカショーが定期的に行われています。そして、町中なので、自分たちで音量規制を設けています。去年は幕間がイルカショーになるようにプログラムを組んでいたのですが、さすがに時間管理が難しいんです。それにステージは一つなので転換に時間がかかる。そこで幕間はサラームさんにDJをお願いしようと」
サ「DJはクラブでやるようにノンストップで曲を繋いで、お客さんを踊らせる感じですか? それともラジオ番組のように「これはどこどこの曲で、こういういわれがあります」と話して曲をかけるのがいいですか?」
岸「後者がいいです!」
サ「先日、高崎のライヴハウスからU-zhaanのインド古典ライブのオープニングDJとして呼ばれたんです。二部入れ替え制で、一部は午後3時スタートでした。オープンした途端にお客さんがダーっと入ってきて、コンクリートの床に持参した段ボールの切れ端を敷いて、ステージに向かって座ってしまったんです。床座りで満員になった状態で、ぼくは1時間半DJやることになった(笑)。中にはDJの僕に向かって”ライブはいつ始まるんですか?”と聞いてくるオッチャンもいて、もう失礼な!(笑) そういう状況でブンブンブンとダンス音楽をかけ続けるのも大人げないので、マイクを借りて”これは西アフリカのニジェールのサハラ砂漠に住むトゥアレグ族の祈祷音楽です”などと曲の解説を交えながらプレイしましたよ」
岸「そんなかんじで。基本は喋りながら音楽をかけて、どうしてもお客さんを踊らせたい時は、インドのハウスなんかかけて下さいよ」
サ「それは楽しそうですね」
岸「彼岸なのでまだまだ西日は暑いですが、楽しいことを一緒にしましょう!」
サ「お誘いいただきありがとうございます!」