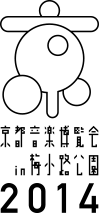音博の楽しみ方 その6
くるりと女の子について
鹿野 淳(MUSICA)
くるりのことは大好きだが、同時にとても苦手だ。
それは僕が一人っ子かつ男子校出身だからな気がしている。
男子校の学生にとって女子は神様のようなもので、どうしょうもなく好き焦がれる存在だが、好き過ぎて、そして日常の傍らに居なさ過ぎて、いざという時に意識し過ぎて大外ししたり空振りを繰り返す。つまりは大好き過ぎて、苦手なのだ。
何が言いたいのかと言えば、くるりってどこか女の子だなあと思うのである。勿論岸田のルックスに対してではない。さとちゃんのそれは観ようによっては女性的だが、そんなことを言いたいわけではない。さらに言えばファンファンのことは残念ながらよく存じ上げていないし、彼女はとても乙女のようにも見えるので、恥ずかしくてなかなか一緒に話せないでいるが、そういう話でもない。
くるりという音楽が、とても女性的だなあと思うのである。
僕は英語もロクにわからないまま悦に入って洋楽のロックを聴いて語り尽くした世代のど真ん中なので、その音楽がどんな歌詞なのかよりも、まずは音楽自体の雰囲気を大切にする。その意味でくるりの音楽は、とても「匂い」や「雰囲気」が強い。まるでどこか女性のうなじを思わせるような、秘めやかで肉体的で、しかも恥ずかしげなもの、それが「マイくるり」なのである。デビュー曲の“東京”はまさにその極みで、あの曲本来の意味は横に置かせてもらい、勝手に今は何をしているかわからない、北鎌倉の駅でよく話をしたうなじの綺麗な女子高生から久しぶりに手紙をもらった気になって聴いていたことがある。言うまでもなくそんな歌詞ではないのだが、そういう和製の妖艶さをくるりの音楽は放っている気がしてならないのだ。そしてその女性らしい奥まった恥じらいのようなものこそが、くるりの音楽を今も新鮮に響かせ、しかも彼らをずっと前線にいさせている原動力の気がするのである。
くるりが何故ここまで息の長いバンドであり続けているのか? その答えは様々な部分にあると思うが、同じ時代にシーンを彩ったバンドが殆どいなくなってしまっている現在、そんなことを少しばかり考えてみるのも面白いかもしれない。
勿論、彼らの楽曲性が高いこともあるし、様々な国のルーツミュージックに対応出来る音楽の本質がしっかりしている部分もある。アルバム毎にテーマが鮮烈なまでに変化して行き、同じような音楽を何度も作らないのに「くるりカラー」がちゃんとリスナーに根付いている部分も彼らの大きな魅力だ。
ただ、それだけではなく、「くるりは中性的だからこそ素晴らしい」と思う。
前述したように、岸田の作る音楽やメロディはとてもしなやかで、僕はそこから女性のような色気を感じる。しかし実際の岸田の音楽に対するアグレッシヴな向かい合い方はとても男性的であって、なかなか彼の底を知るのは難しい。
さとちゃんのベースは、8ビートをランニングさせる時のグルーヴ感や安定感からも明らかな様にとても男性的なタフなものだが、彼がノイズ・マッカートニーで果たしている役割や、岸田との長きにも渡るコンビネーションを観ると、その繊細さや丁寧さにおいて極めて女性的なものを感じる。今回の原稿のオファーも彼自身からいただいたが、非常に丁寧かつ柔らかなものだったと記憶している。
この2人のお互いを補填し合う関係性こそが、くるりを長続きさせているものでもあり、ファンファンを始めとする世代や国籍を超えた数々の素晴らしいアーティストとの出逢いと別れを生み出している部分でもあり、音楽性的にも絶妙の化学反応を起こさせる所以なのではないか? 実際にこのバンドのファンは、他のバンドと比べて男女比がかなり均等化している。強引な意見かもしれないが、僕のようにくるりの楽曲に女性観を見つけ、そこに惹かれている男性リスナーは多いんじゃないかなと思う。そう言うところを含め、くるりの中性性、つまりは岸田とさとちゃんという男性2人の中にある女性的な部分は、このバンドのとても大きな武器なのだ。
そんなくるりの本質を毎回体現している京都音博でも、毎年ユニークかつ音楽的な性別を超えたブッキングがみられ、とても楽しい。しかも女性アーティストの登用がとても上手いしラジカルだ。ーーここに今まで綴って来た事が繋がるという、強引なコラムがこれである。
女性アーティスト的には初年度にCoccoに加え、リアダンというアイルランドのケルト民謡性を持った女性アンドを呼んだのは当時はかなり驚いたが、その後3回目(5回目も参加)に石川さゆりという誰も考えつかなかったブッキングを果たし大盛り上がりを見せたのはご存知の通り。5回目にはスウェーデンのマイア・ヒラサワというポップディーヴァを呼んだり、京都音博のラジカルなブッキングは、くるりの音楽に対する自由で奔放な本質をそのまま体現していると言えよう。
今年も椎名林檎という、なかなかフェスには参加しないディーヴァが、あの地でどんなライヴをするのかが楽しみでならないが、同時にもう一人、斬新な女性アーティストが出演する。それがレバノン出身のヤスミン・ハムダンだ。
ヤスミンは現在37歳、その妖艶な美貌と音楽に魅せられる世界中のインディーズファンが後を絶たない女性アーティストである。
そもそもはレバノンの首都ベイルートで、Soap Killsというバンドで歌っていたヤスミン。このバンドは「中東のマッシヴアタック」と言われていたバンドで、その界隈では評判が高かったが、惜しまれながら解散してしまった。その後ソロとして彼女は拠点をパリに移し、そこでマドンナのアルバム『MUSIC』のプロデューサーとして一躍名を馳せたミルウェイズとのユニットを結成し(彼はアフガン系のフランスを拠点とするアーティストだったので、共鳴すべき所が多かったのだろう)、『Y.A.S.』というアルバムをリリースした。
その後、まさに満を持して作った初のソロアルバム『Ya Nass』は、ベルギーのレーベルからリリース。世界を股にかけて奔放な活動と音楽を制作し続けたヤスミンはこのアルバムで、重苦しくもありながら浮遊感すら感じる不思議なトラックと、その上を謎の呪文のように這うダークかつ独特の言葉のリズム感を放つ妖艶なる歌唱で、世界中のインディーズシーンを虜にする音像を作り上げた。もうね、聴いているだけでクラックラするね。頭の中も目の前も耳の中かっぽじったその奥までもが、クラックラする。
中東からヨーロッパまでを自由に行き交うヤスミンの音楽は、アメリカのロードムーヴィーのゴッドであるジム・ジャームッシュの目にとまり、彼の最新映画『オンリー・ラヴァーズ・レフト・アライヴ』の重要なシーンでは、彼女が一曲丸ごと歌うシーンが使われている。この映画はジャームッシュ史上最も明快なストーリーを持った「ドラキュラ映画」で、ヤスミンはまるでドラキュラのように魂を吸い尽くすような歌唱をここで披露している。時に映画の中で音楽はストーリーを無視する程の強いオーラとイメージを植え付けるが、ヤスミンの歌と容姿とトラックの雰囲気は、まさにそれだけで立派なロードムーヴィーのようなものだと思う。
ロックとかポップミュージックとか、ダンスミュージックとかチルアウトとか、日本のみならず世界中にはよくも悪くもカテゴリーやジャンルがあって、その表向きの秩序の中で様々な音楽はリスナーの引き出しに収まってゆく。しかし、そういうシーンの中にはいつでも簡単に引き出しに収まらない自由な音楽があって、くるりはそう言う音楽を見つけ導く名人なんだと思う。というか、石川さゆりへのお誘いが顕著なように、例えば演歌という括りに収まらない、音楽やアーティストの本当の姿をリスナーの下に導くのが好きだし上手いのだろう。それは彼らの『TEAM ROCK』や『ワルツを踊れ』というアルバムなどが証明している。さらに言えば、京都音博のような独特のステージを与えられた時の素晴らしき女性アーティストの本気は、まるでウッドストックのジャニス・ジョプリンや初年度ライジング・サン・ロックフェスの椎名林檎のような、もの凄いマジックを生む。それもまた、音楽フェスならではの醍醐味である。
ジム・ジャームッシュからヤスミンへのプロポーズだった映画は素晴らしかった。では、くるりからヤスミンへのプロポーズなる今年の京都音博は、どんな愛の響きとマジックを生むのだろう? 京都という国境を越えた趣きと、くるりという性を超えた感性が、ヤスミン・ハムダンとどんな交配を果たすのか?
京都音博、いざ来る。
鹿野 淳(MUSICA)